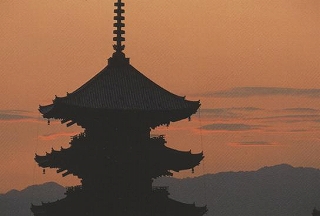 元治元年六月五日、新撰組は池田屋を襲撃した。その後も会津藩と新撰組は、不逞浪士の取締りを続けていた。この刀の持ち主である、柴外三郎の実弟、柴司(しば つかさ)は、新撰組とともに探索の任についていた。この頃、新撰組だけでは手が足りず、会津藩から若手の藩士が助っ人にかり出されていたのである。司もその中の一人であった。
元治元年六月五日、新撰組は池田屋を襲撃した。その後も会津藩と新撰組は、不逞浪士の取締りを続けていた。この刀の持ち主である、柴外三郎の実弟、柴司(しば つかさ)は、新撰組とともに探索の任についていた。この頃、新撰組だけでは手が足りず、会津藩から若手の藩士が助っ人にかり出されていたのである。司もその中の一人であった。その五日後の六月十日、司らは新撰組の武田観柳斎の指揮のもと、祇園の南にある茶屋明保野亭を探索した。すると、数人の浪士が逃走を謀ったので、司は一人の浪士を槍で突いた。致命傷には至らなかったが、捕らえてみると麻田時太郎と名乗る土佐藩士であった。麻田は、その翌日武門の恥として意地腹を切ってしまたのである。長州系の倒幕浪士の中に麻田が居たということは、やはりやましい事でもあったのではないか?現に、その後土佐は倒幕の優藩となったのだから、切腹の密命でもあったのかも知れない。
いずれにしても、会津藩としては困った事態である。会津と土佐の対立問題となりかねない。会津藩としては、司に切腹を命ずるより仕方がなかった。介錯を命じられたのは、司の長兄である幾馬であったが、次兄の外三郎のほうが剣の腕に覚えがあるということで、この刀の持ち主である外三郎が行うことになった。その前夜には、兄弟、親戚、友人が集まって永久の別れを惜しんだ。その中には、後の陸軍元帥柴五郎や、東大初代総長の山川健次郎もいた。司とは、従兄弟どうしなのである。
会津藩主中将松平容保は、司に新たに二百石の家督を与えた。これは、当時としては破格のことで、容保も余程気が引けたのだろう。司の切腹の後、この家督を継いだのは外三郎である。
その時に、司を介錯した刀が、この会津道辰かも知れないのである。私は、この物語が掲載されている本(写真)を見つけ、早速著者にお手紙を差し上げ、刀の写真と押し型をお見せしたところ、この刀の製作が文久二年であることや、これだけ茎に刻み込んだ意気込みからして、ほぼこの刀に間違いないであろうとの、ご返事を頂いた。
この刀が私の手元にあることが、私には不思議でならない。この刀は、私が抜刀術を習った師である刀剣商が、アメリカのオークションで仕入れてきたばかりの、里帰り品の中から見つけたのである。売った本人も、この刀の由来は調べぬままに私に売ったらしい。未だに会うたびに、「あれを是非買い戻したい。」と言われて困っている。当時私は、まだ二十代後半だったので、これを購入するのは経済的にずい分大変だった。毎月いくらでもいいから、払ってくれればいいと、信用で売ってくれたのである。
その時思い出したことは、司馬遼太郎の「燃えよ剣」の中の一説である。主人公の土方歳三が、刀を求めて刀屋を捜し歩いていて、偶然入った古道具屋で、破格の値段で「和泉守兼定」を譲ってくれるという主に対して、「何故だ」と聞くと、「刀にも運賦天賦の一生がございます。・・・・中略・・・・・数百年間、この刀はあなた様に会いたがっていたのだろう。手前には何となくそういうことがわかります。五両が不満なら差し上げてもよろしゅうございます。・・・」
何かの縁というか、この刀の意志か、あるいは外三郎、司の意志が私に託してくれたような気がして、今でも大切に保管している。
また、会津藩士中二番隊の隊士であった、酒井峯治という人の「戊辰戦争実歴談」という私記が、会津の白虎隊記念館に残っている。
―柴某アリ。五軒町ヲ西ニ向カッテ進ムニ、鎧ヲ着シ、長刀ヲ揮ッテ躍リ入ル。柴某、外二三ノ勇壮、其勢ヒ、実ニ云フベカラズ―
とある。
また、柴五三郎(柴五郎の兄)の私記に、「柴外三郎の活躍」として記されている。
―九月十四日、南町口土手の上、見居りしに、城中より白虎隊の鯨波を揚げて出るを、吾同姓外三郎も土手に居たるが、杖つきたる薙刀を振り舞し振り舞し、打交じりて駆出したり。暫くして戻り、曰く。「子わっぱの餓飢共、可愛そうにのみ思い出しに、他のズナイ野郎共が命惜しそうにマゴマゴ進み得ぬ処を、彼の子児供等のみ憶する気振りもなく、目白の囀る如き細声を揃えて進み行くを見ては、思わず知らず弥次馬したり。迚も感心せり、感心せり。実に涙の出るぞかし。―
実は、柴家の子孫の方が、今でも東京都内に健在で居られる。正確には、長兄の幾馬の末裔の方である。数年前に、新撰組研究家で著書も多数出している赤間倭子先生より紹介して頂き、この刀をお見せすることが出来た。
いつかは、京都黒谷の金戒光明寺の司の墓前にこの刀をお供えして、供養して差し上げたいと思っている。
